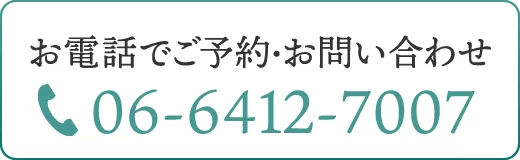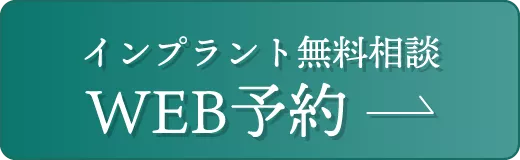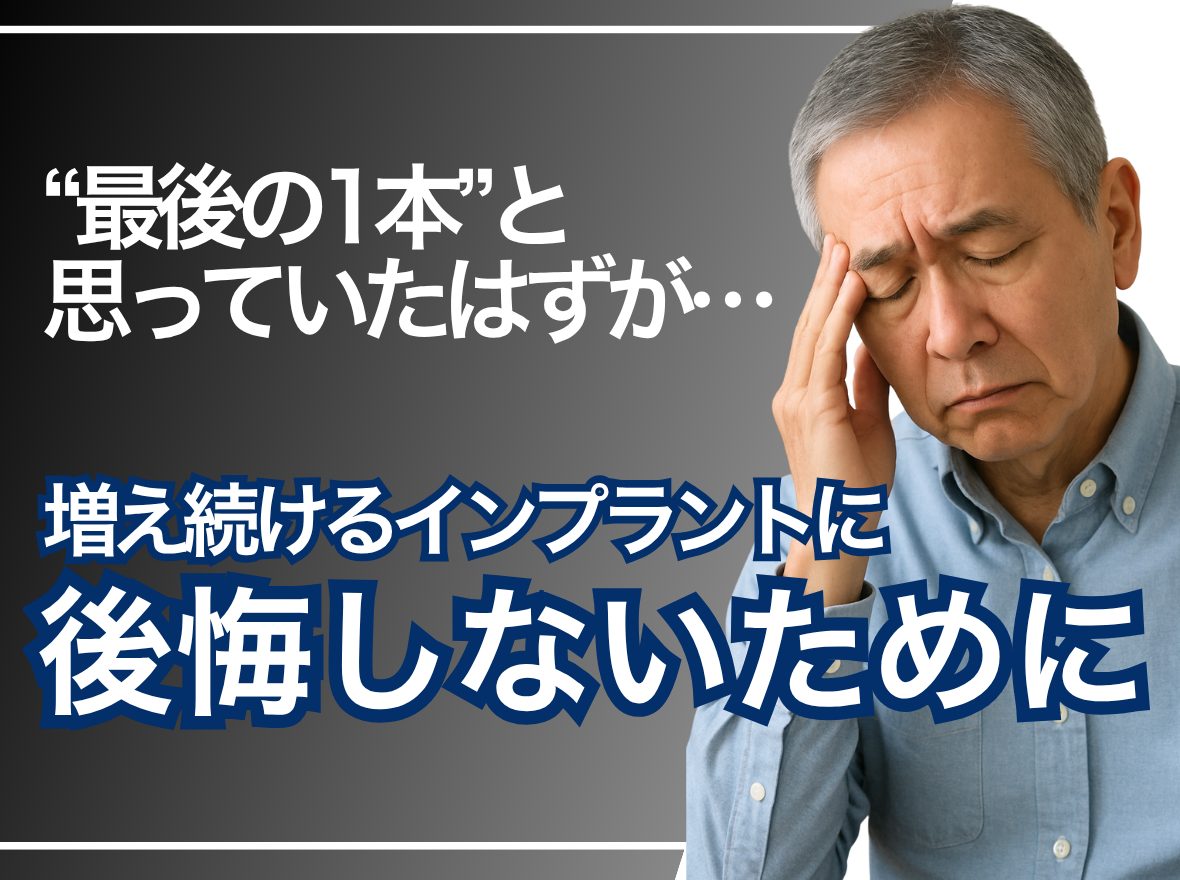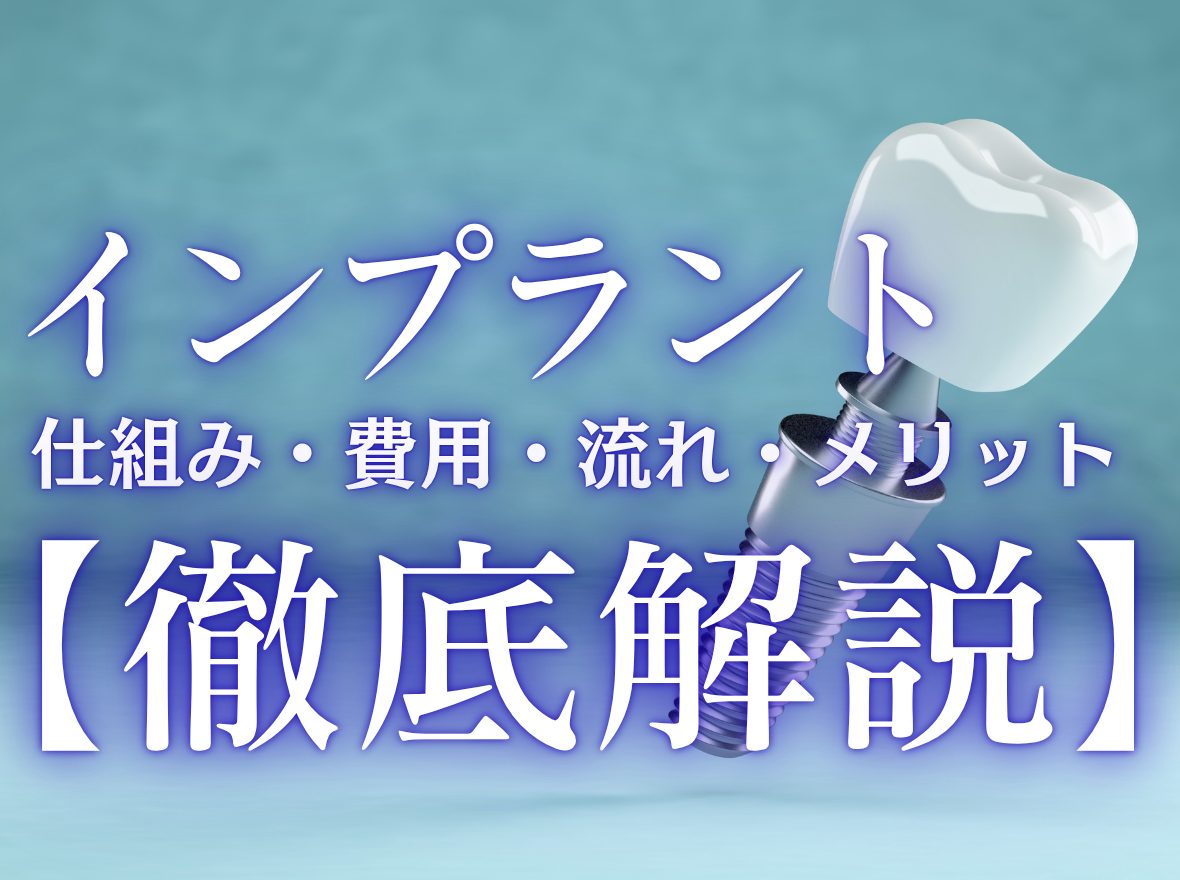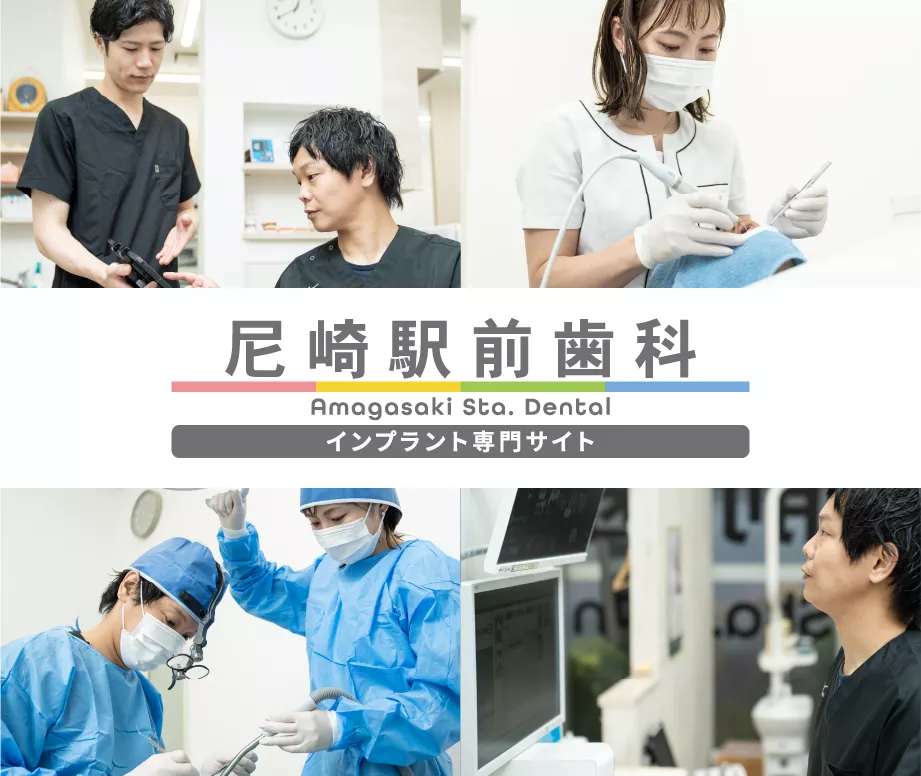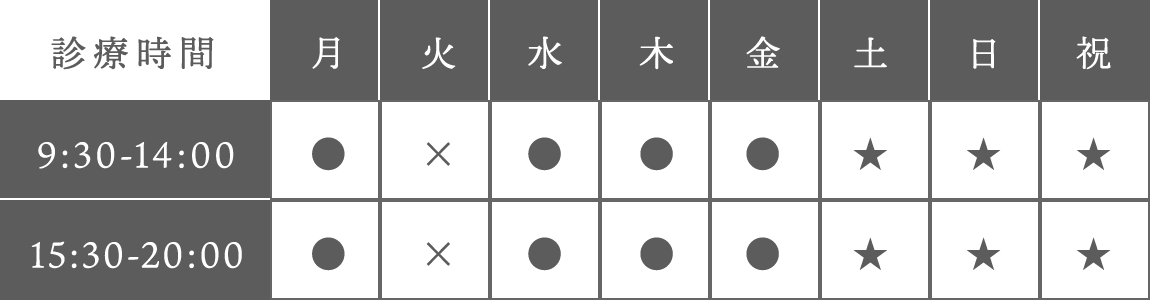― インプラント治療における骨造成の考え方 ―
目次
なぜ「骨」がインプラントに必要なのか
インプラントは、歯を失った部分の骨の中に人工歯根(インプラント体)を埋め込む治療です。
つまり、骨がしっかりしていなければ、インプラントを支えることができません。
しかし、抜歯後の時間経過や歯周病などの影響で骨が痩せてしまい、
「骨が足りないからインプラントは難しい」と言われるケースも少なくありません。
そうしたときに行われるのが、**GBR(Guided Bone Regeneration:骨再生誘導法)**です。
GBR(骨補填材)とは?どんな役割があるのか
GBRでは、骨補填材(人工骨など)を用いて、骨の再生を促す処置を行います。
骨補填材とは、骨が欠けている部分に入れ、**骨が再生するための「足場」**を作る材料のことです。
主に次のような種類があります。
| 種類 | 主成分・特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 自家骨 | 患者さん自身から採取した骨。最も骨になりやすい | 骨採取が必要 |
| 人工骨 | β-TCP、ハイドロキシアパタイトなど人工的に作られた材料 | 安全性が高く一般的 |
| 異種骨・同種骨 | 動物由来またはヒト由来の骨を加工したもの | 骨誘導能を持つものもあり |
補填材自体が「骨に変わる」わけではなく、骨ができるための環境を整えるものです。
骨が少なくなる原因
骨が足りなくなる背景には、いくつかの要因があります。
・歯周病:炎症によって歯を支える骨が徐々に溶けていく
・抜歯後の骨吸収:歯を抜いたまま放置すると、骨が自然に痩せてしまう
・欠損部の放置:噛む力がかからず、骨が萎縮していく
・外傷・感染:事故や歯根破折によって骨が失われることも
このようなケースでは、骨造成(GBR)によってインプラントを可能にすることが目的となります。
骨補填材で「本当に骨はできる」のか?
多くの方が「人工骨を入れたらすべて自分の骨に置き換わる」と思われがちですが、実際は少し違います。
・骨補填材の周囲に血管や細胞が入り込み、
・徐々に骨が再生し、
・一部の補填材は吸収されず残存する
つまり、完全に天然の骨に戻るわけではなく、補填材と新生骨が混ざった複合的な組織になります。
それでも、適切な設計と安定性が確保されていれば、インプラント治療に十分耐えられる状態になります。
骨補填材の種類と特徴
骨補填材は、大きく吸収性と非吸収性の2種類に分かれます。
吸収性の骨補填材
時間とともに体内で吸収され、自分の骨に置き換わるタイプです。
| 材料 | 主成分 | 特徴 | 商品例 |
|---|---|---|---|
| β-リン酸三カルシウム(β-TCP) | Ca₃(PO₄)₂ | 吸収が早く骨置換が起こりやすい | オスフェリオン®, トリオス® |
| ハイドロキシアパタイト(多孔性) | Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂ | 吸収は遅いが骨伝導性が高い | アパセラム®, ネオボーン® |
| β-TCP+HA複合材 | β-TCP + HA | 吸収速度のバランスが良い | MBCP®, ボーンセラミック® |
非吸収性の骨補填材
体内に長く残り、形態や体積を保持しやすいタイプです。
| 材料 | 主成分 | 特徴 | 商品例 |
|---|---|---|---|
| ハイドロキシアパタイト(緻密タイプ) | Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂ | 長期間残存し、スペース維持に優れる | アパタイトブロック® |
| チタンメッシュ | Ti | 形態保持・スペース確保に有効 | Tiメッシュ®, Tiボーンケージ® |
| バイオガラス | SiO₂-CaO系 | 骨伝導性と生体親和性を両立 | Bioglass®, バイトラボン® |
どの材料を選ぶかは、部位・目的・感染リスク・骨の性状などを総合的に判断して決定します。
骨補填材のメリット・デメリット
メリット
・骨が足りない部位にもインプラントが可能になる
・噛み合わせや見た目の回復がしやすい
・治療の選択肢が広がる
デメリット
・感染や腫れなどの術後リスクがある
・補填材が完全に骨に置き換わらないことがある
・治療費・期間が増えることがある
「骨ができる=良い治療」とは限らない理由
GBRは非常に有用な技術ですが、すべての症例で行うべきとは限りません。
骨補填材は身体にとってはあくまで“異物”であり、必要最小限で行うことが理想です。
大切なのは「骨を足す」ことではなく、
・どの位置・角度でインプラントを入れるか
・骨補填をしなくても済む設計ができるか
・骨を守りながら治療を進められるか
といった治療計画と技術力です。
GBRを行う前に知ってほしいこと
GBRはインプラント治療の可能性を広げる非常に優れた技術です。
しかし私は、「可能な限りGBRを行わない方が良い」という立場を取っています。
その理由は、
・GBRが完璧な骨再生を保証するわけではないこと
・補填材によっては、長期的な骨の安定性に不確実な点があること
・手術回数・腫れ・痛みなど、患者様の負担が増える傾向があること
だからこそ、私たちは**「骨を守る」「抜歯時から骨を残す」**という設計を重視しています。
必要な場面では的確にGBRを行い、そうでない場合は極力シンプルに、
「自分の骨を最大限活かす治療」を心がけています。
まとめ:必要最小限のGBRで、最大の結果を
・GBRは「骨が足りない場合に行う補助的な治療」
・骨を作ることより「長期的に噛める状態を作ること」が最も重要
・当院では、最小限の補填材で最大限の安定を目指す設計を行っています
骨が足りないと言われた方も、諦める必要はありません。
状態を正しく診断すれば、最適な治療の可能性は広がります。
ぜひ一度、現在の骨の状態を詳しく検査してみましょう。

・他院で抜歯してインプラントと診断されたけど、歯を残せないの?
・インプラントはしたいけど、費用は抑えたい…
・治療方法や痛み治療期間など、治療の詳細を聞きたい
・どれくらい持つのか、トラブルはないのか 等
些細なことでも、気になることがございましたら、お気軽にご相談にお越しください。
【執筆・監修者】
尼崎駅前歯科
院長 鷲本 剛
虫歯治療や歯周病治療などの一般的な歯科治療に携わりながら、歯を失った患者様に対する治療にも力を注ぐ。
治療技術、知識の研鑽の為、インプラント治療や矯正治療を専門に扱う様々な歯科医院にて診療を行いながら、国内外の学会や研修会に参加し、最新の技術や知識を学び、所属している大阪歯科大学口腔インプラント科では、専門的な診療や手術に携わる機会を得て、より高度な技術や知識を身に付ける。
現在は、培った知識経験を若手医師の育成のため、歯科医師に向けインプラント治療のセミナー講師も務める。

◇当院のインプラント治療について
https://www.amagasaki.dental/implant/